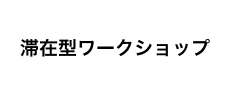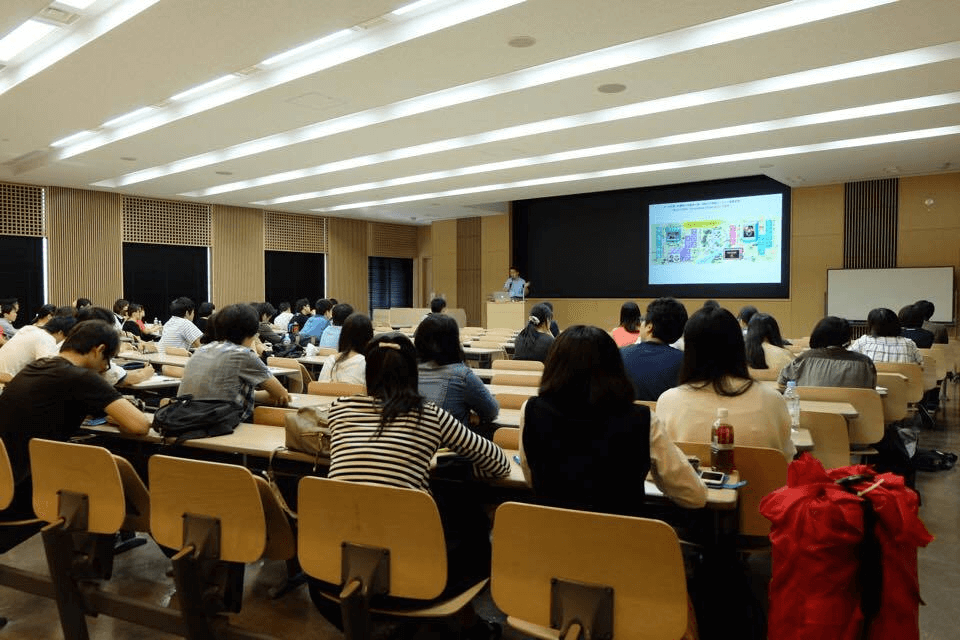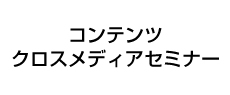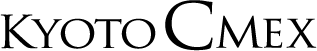- Home
- インタビュー・講演録, ニュース
- 【京都ヒストリカ国際映画祭】 京都文化博物館・学芸課映像情報室長の森脇清隆様インタビュー後編。 京都の映像文化を若者に受け継ぐ
【京都ヒストリカ国際映画祭】 京都文化博物館・学芸課映像情報室長の森脇清隆様インタビュー後編。 京都の映像文化を若者に受け継ぐ
- 2022/1/7
- インタビュー・講演録, ニュース
- 2,212

【京都ヒストリカ国際映画祭】関係者インタビュー第3弾後編
京都ヒストリカ国際映画祭/京都文化博物館 学芸課映像情報室長 森脇清隆氏
【立命館大学映像学部×京都ヒストリカ国際映画祭】
立命館大学映像学部ではこれまで、KYOTO CMEXに関する様々なイベントの運営や広報活動に取り組んできましたが、今年は公式サイトで関係者インタビューを行うことになりました!
第3弾の今回は、京都文化博物館の学芸員でもあり、京都ヒストリカ国際映画祭や京都フィルムメーカーズラボにも携わっている、森脇清隆氏にお話を聞きました。
こちらの記事は後編です。前編はこちら↓
—https://cmex.kyoto/2022/01/05/33744/
―――
京都ヒストリカ映画祭での上映作品を選ぶ
―――
Q 京都ヒストリカ国際映画祭ができた背景は何ですか?
森脇清隆氏(以下、森脇):映画祭って単なる作品上映会だけではないんですよ。映画の作品って色々な尺度がありますけれど、映画祭が作品の価値、つまりは作品の値段を決めている部分って非常に大きいんですね。権威のある映画祭で賞をもらったら、今までは3ヶ国しかリリースできなかったのが、一気に50ヵ国にリリースできるようになる。ということは、収入も何十倍になり、かつ、その実績を持って、次の作品の資金を調達するのが一気に容易になる。映画は、文化芸術っていう形に見えていますけれど、実際は、産業・興業であったりお金儲けだったりするんですよ。日本の多くの映画祭はそういった国際映画祭のあり方の輪の中にまだ入れてないんですね。そういった背景もあって、京都ヒストリカ映画祭を、ぜひ、国際映画祭の輪の中に入れていきたいという思いで始めました。また、例えば、ベルリンでは、国際映画祭があって、その下にタレントキャンパスがある。この仕組みが大事なんですね。ベルリン国際映画祭っていう権威のある賞があって、そこが育成している若手がいる。このようにくっついていることで意味があるんですね。ヒストリカも、京都ヒストリカ国際映画祭があって、その一部門としてフィルムメーカーズラボはあるっていう感じですかね。
Q 京都ヒストリカ国際映画祭でどのような役割をされていますか?
森脇:映画祭のスクリーニングの企画にはスペシャル部門であったり、あるいはワールドって言われている部門だったり、後はレトロ部門とか、いろいろな分類があります。その分類の中で、私が担当するのはレトロ部門やスペシャル部門で、一番メインになっているのは、レトロ部門、歴史の部門ですね。例えば、溝口健二監督の『近松物語』っていうのが4Kで復元されたとします。そこで、「4Kでの復元にはこういう意味があるんですよ」ということで上映したり、『近松物語』の意味を実感してもらうためには、この映画とこの映画も一緒に見てもらった方がより理解が深まるということで特集上映したり、そういうキュレーションを行っています。あとは、京都文化博物館のシアターが会場になっているので、汗かく量としては映画祭運営が一番多いですかね。
―――
京都ヒストリカ映画祭の人材育成部門「フィルムメーカズラボ」の歴史とこれから
―――
Q フィルムメーカーズラボができた背景はどういったものですか?
森脇:京都文化博物館は文化施設ですが、映画産業の振興をやっていこうとなったのは2006年あたりです。映画会社の人だったり、立命館大学映像学部の細井先生や中村先生と韓国の映像産業の視察に行ったり、京都府が映像文化振興のための「太秦プロジェクト」を行っていたのが2006年ぐらいですね。そして、2007年に、博物館と交流のあったドイツ文化センターが、ベルリン国際映画祭を手本にして京都で若手映画制作者向けのワークショップをやろうということで、その下見として、私と東映撮影所の高橋さんが一緒にベルリンに行き、映画祭の機能や映画産業を振興する手法、若手から新しい映画を作り出す手法を勉強させてもらいました。また、ベルリンでは観光と映画産業を連携させて振興するということも学びました。観光が伸びれば伸びるほど文化の振興にお金が入ってくという仕組みをベルリン(国際映画祭)は作っていたんですね。それは、とても勉強になりましたね。また、2008年に、ベルリン国際映画祭のタレントキャンパスのディレクターであるドロテー・ヴェナーという人に京都に来ていただいて、『ドロテーさんを囲む会』というのを開きました。東映の方や松竹撮影所の方など色々な方に来ていただいて、「京都ってこれだけ映画の歴史もあり、かつ可能性もあって、これからこんな仕組みを作っていくようにしたいと思っていますよ」という対談をしました。そして、とにかく京都でできるワークショップを1回やってみないとだめだ、ということで、短編時代劇を作るワークショップの第1回っていうのを2008年に立ち上げたんですね。それがフィルムメーカーズラボのスタート地点ていう感じですね。
Q どのようにして海外から参加者を集めていますか?
森脇:広報の部分で、我々が世界の人に声かけるとなると、はじめは何をしていいか全くわからないレベルだったんですね。そこから、SNSを耕していこうか、ということになり、facebookを始めました。そのきっかけになったエピソードがあります。リトアニアから来て、時代劇を一緒に作った女性がいたのですが、リトアニアに帰って「京都のフィルムメーカーズラボが面白かった」という宣伝をSNSでいっぱいしてくれたんですね。すると、その次の年にリトアニアから「参加したい」という声が沢山来ました。こういった、SNSというプラットフォーム上の口コミ効果を期待するためにはやっぱりSNSを日頃からしっかり耕さないとダメだなっていう…今でも耕し続けています。
また、イタリアの政府の組織であるイタリア文化会館が一緒にやりましょうっていうことでヴェネチア・ビエンナーレの若手映画人への制作支援部門のビエンナーレ・カレッジ・シネマと繋いでくださったんです。ヨーロッパで『アジアの人材』をピックアップしようと思っても、なかなかいい人材が見つからない。ヨーロッパの人たちは、ビジネスをする時に、評判やインターネットの情報より信頼できる友達の情報をもの凄く大事にするんですね。きっとこれは中国や他の国でも同じなんですけれど。自分が信頼できるアジアの人経由でいい若手をピックアップしてきたい、という思いがあるようです。そういう経緯もあって、今、ヴェネチア国際映画祭のビエンナーレ・カレッジ・シネマのアジアの窓口的な形で連携しています。
Q フィルムメーカーズラボの今後の課題はなんですか?
森脇:クリエイターの育て方というか、クリエイターへのインセンティブの提供の仕方と、いい人材の確保です。東京国際映画祭に審査員で来た海外の映画祭ディレクターの方に審査が終わった後に京都に遊びに来てもらっています。その際に、フィルムメーカーズラボに来た作家と会話してもらう。後々、フィルムメーカズラボに参加してよかったっていう口コミが来る理由の一つは、映画祭のディレクターと直接ご挨拶、名刺交換ができるということなんですね。映画祭の作品を募集すると、応募は山ほど来るかもしれないけれど、本当にいい作品が来るとは限りません。ディレクターって常に人を、才能を探していているんです。なので、フィルムメーカーズラボに来てもらって、例えば、京都で時代劇作りたいと考えている作家と交流してもらうとします。すると、「作品ができたら送りなさい」「見てあげるから、よかったらコンペに応募して来なさい」「コンペよりもこっちの方がいい」「他のいい映画祭があったら紹介してあげる」などといってもらえるかもしれません。だから、京都のラボとして、良い人材を確保しないといけないというのが今後のフィルムメーカーズラボの課題ですね。京都にいい人材がいるよ、フィルムメーカーズラボで人材を紹介してもらえるよ、ということになれば、映画祭のディレクターたちのネットワークでの評判も上がりますから。「タレントの確保」が、これからの課題かなっていう感じですかね。
Q コロナによって学んだことと、コロナ禍を通じて感じた今後の展望は何ですか?
森脇:実はコロナ以前から効果を期待できた方法などで、コロナ禍という状況で考えざるをえなくなってしまって、思いついたのが、コミュニケーションソフトの有効活用ですね。例えば、京都のラボは二日間で時代劇を撮るんですけど、以前はそのシナリオや前作業について、撮影する前に実際に会って話し合っていたんですね。けれども、現代ってコミュニケーションソフトなど、使えるものが実はたくさんあったんです。実際に会って作業や議論をしなくても、事前にネット上でかなりグループワークができたっていうことに気づかされました。そういうのを去年から、コロナを機会に導入したって感じですかね。ワークショップだけじゃなくて、講演やセミナーっていう部分でも変わったことといえば、講演会やセミナーでお話してもらう時に、質問事項を事前にある程度もらって内容をシャープにして、かつ、そのお話の内容を事前に参加者に渡しておくようになったことですね。聞く人も興味をフォーカスしやすく、話し手も内容にフォーカスしやすいものになる。それがいいかどうかわからないんですよ、もっと突然の出会いとか計算されないものに面白さがあったりするので、いいかどうかはわからないですけど。コロナで気づかせてもらったって感じです。でも、コロナ禍であるからこその人と人の距離感っていうのを演出に使う人はまだ少ないですよね。若い人たちは自分たちのコロナに対する感性を作品にどんどん出していったら、それはそれで歴史的な作品にもなるんじゃないかなと思うんですけれども。
―――
時代劇が未来の映画表現の幅を広げる
―――
Q 総じてフィルムメーカーズラボが映画業界に貢献していると感じておられますか?
森脇:なかなかシビアな質問ですね、成果って。映画表現とかで映画が誕生して125年ぐらいになるんですけど、映画表現って全世界を回っているんですよ。例えば、スターウォーズっていう作品があったとしたら90分のうち30分くらいはライトサーベルでの殺陣でしょ。ライトサーベルって握っている時の左右の握りの間に空間があるんですよ。つまり日本刀がモチーフなんですね。ライトサーベル、刀を持った人がチャンチャンバラバラ。黒澤明の殺陣はある緊張した瞬間から一瞬でズバッとどちらかがが勝つってパターンですね。こういう殺陣もあれば、スターウォーズやっているのは、ジャーンジャーンジャーンジャーンっていう歌舞伎とか長谷川一夫がやっている殺陣なんですね。そして、鍔迫り合いの緊張をどう撮るのか。鍔迫り合いしている刀を真ん中にして。こっちから取ったらこの人の顔がアップになる、そして刀も入る。次は反対から。スピルバーグ本人も言っているんですけど、明らかに日本刀の殺陣なんですよ。時代劇なんですよ。真似されて、儲けられて損したって話じゃなくて、みんなが楽しんで、そこにお金入って儲かったら、それはハッピーじゃないですか。そして、日本刀とわからずとも、みんなの頭の中に、日本刀の殺陣ってかっこいいっていうのが残ったらいいんですよ。すると、次に日本の時代劇の殺陣を見た時に何の違和感もなく見れるわけですよね。他にも、例えば、江戸時代の居酒屋には実際はカウンター席はないです、歴史的には。カウンターで椅子に座って肘ついているなんて構図は歴史的には絶対ないです。けれども、みんなの頭の中の江戸時代はそういった京都の映像製作者達に騙された江戸時代の像が入っているんです。それぐらいの映像表現って今生きている人の中に積もっているんですね。だから何が成果か、業界にどれだけ貢献したかっていうのは、やっぱりトータル的な話だろうなと。海外から来る人が自分の国に帰って自作の中で日本刀の殺陣がしたいかって言ったら、それは少ないですね。ただ、フィルムメーカーズラボに来た人が、参加した動機として言っていたのが、「ギャングの映画を帰って作らないといけないのでで、侍の「所作」や侍みたいな凄みを現代のギャングの親分にさせて表現したい」ということでした。ですから、京都映画の表現を真似してもらえたというは、私は成果だと思うんですね。お金では買えない成果だと思っています。そして、フィルムメーカズラボに来た作家の中に、それが縁で東映撮影所や松竹撮影所で働いている人もいるんですよ。あとは、撮影所を使ってちょっと撮影したり、あるいはテレビのCMを撮ったりとか。それまで、ニューヨークから来た人たちが東京でやっていた日本ロケを、京都でしたりとか。そういうのも、最近はじわじわ発生しています。こういうことを続けていくのが一番大事なんじゃないかなと個人的に思っています。アニメやマンガでは時代劇全盛ですが、実写の時代劇がアニメの時代劇ほどもてはやされないのは、私は単純にお金の問題じゃないと思っています。だからそこで歴史研究している人やアニメの時代劇が好きな人が一緒になって実写の時代劇ってどうなのか、もっとこういう形もあるんじゃないのかみたいな話をして、一緒に努力していくという貢献はできるかなという感じですかね。もちろん、できればそこにお金がどんどん落ちるようになったらいいなと思っています。